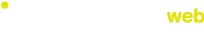インフォメーション 3
3年連続の出前授業をVECが実施。
プラスチックの理解を深め、探究学習の扉を開く
/福井県立若狭高等学校
2005年からスタートしたVECの出前授業は、体験型の出前授業を目指し実験を通して、①プラスチックや化学に興味を持ってもらうこと②リサイクルの基本である比重分離を体験してもらいながらプラスチックや環境問題をテーマに全国各地の教育機関で実施されています。今回は福井県立若狭高等学校の1年生6クラス約200人に向けて行われた授業をご紹介。汎用プラスチックの種類や特徴、リサイクルの取り組み等、実験を交えながら講義を行われました。

江戸時代の小浜藩の藩校「順造館」の遺構
福井県立若狭高等学校
「異質のものに対する理解と寛容の精神」を養い教養豊かな社会人の育成を目指す、という教育目標を掲げる伝統校。
2011年、2017年と文部科学省の「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」に指定されており、科学技術や理科教育に力を入れている。地域資源活用型の探究学習は、生徒が主体となり専門的な科学研究や実験を通じて、論理的思考力や問題解決力を養っている。授業や課外活動でも「生徒が主役」となる環境が整っており、これにより自発的に学び、考える力を育む教育が展開されている。
講義:プラスチックを知る
現在、私たちの身の回りにはたくさんのプラスチック製品がありますが、それらは化石資源(原油)から精製されたナフサを熱分解して得られる化学物質を原料として作られています。
全体の約80%は汎用プラスチック(PP、PE、PS、PET、PVC)と呼ばれ、強度、耐薬品性や耐候性、透明性など、それぞれの特性を活かして製品の素材として使われています。
そして、プラスチック製品が一般的に使われ始めたのは、ほんの60年ほど前になります。実は人類とプラスチックの歴史はまだ浅くどの様に使いこなしてゆくか、どの様に付き合って行くかが大きなテーマです。
授業の後半はリサイクルの話が中心となります。海外と日本のリサイクルの取り組みの違いについて説明し、日本におけるペットボトルや塩ビパイプの水平リサイクルの取り組みなどを紹介しました。このような取り組みによって、持続可能な社会の実現に向けた努力がなされていることを紹介しました。

実験1:消しゴムを作ろう
一つ目の実験では、生徒たちが毎日使っている消しゴムを手作りしました。消しゴムの原料はプラスチゾル(約1マイクログラム球状PVC粒子を可塑剤に分散したもの)を使います。まず、電子顕微鏡写真を見ながら、加熱条件によって塩ビ粒子がどう変形するのか、そしてその変化がどのように消しゴムの性能に影響するのかを説明し、消字性の高い消しゴム作りに挑戦。生徒たちは、カラフルなプラスチゾルを混ぜ合わせ、自分たちの好きなようにたこ焼き型の加熱器に流し込みます。
出来上がったばかりのまだ温かい消しゴムを手にして、皆でその出来栄えを見せ合う様子は、化学やプラスチックの面白さを実感しているようでした。


実験2:比重でプラスチックを区別してみよう
比重を測定することは、物質を見分けるための大事な手がかりになります。ペットボトルや電線被覆材のリサイクル工程では、回収された製品を細かく砕いた後、比重によって分離していることを説明しました。
この実験では、5種類の汎用プラスチック(PP、PE、PS、PET、PVC)を、3種類の溶液(水、飽和食塩水、50%エタノール)が入ったビーカーの中に入れ、浮いたり沈んだりする様子を観察し、種類を判別していきました。グループになって「これはPPかな、PE?」と確認し合いながら進めて行く様子が印象的でした。
海洋プラスチックやリサイクルなど、多くのテーマがあるプラスチックですが、その特性を理解し、その上でどうプラスチックを活かすか、または他の素材に代替していくか等を社会全体で考えることはとても重要です。
プラスチックという素材を正しく理解し、適切に利用することで、環境への影響を最小限に抑えつつ、持続可能な未来を築くための道筋を見つける必要があることを伝え、今回の出前授業を締め括りました。

身近な自然科学に興味を持ってほしい
今回ご依頼いただいた、野坂教諭にもお話を伺いました。
「基礎科学の講座の一つとして、出前授業を依頼しました。今話題になっているプラスチックや環境問題を専門家から聞ける機会はとても意味のあること。この授業で生徒たちが、身の回りの自然科学に興味を持ち、次の探究へと繋げてもらいたい」(SSH・研究部 野坂卓史教諭)