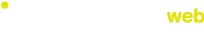リサイクルの現場から
塩ビ管リサイクルの現場から〜 ㈱ムサシノ化学の挑戦
非鉄金属から塩ビ管まで、北海道の資源循環を担って40年。
事業はようやく軌道に

㈱ムサシノ化学(菊地昭好社長、北海道夕張郡)は、北海道における塩ビ管リサイクルの重要拠点。塩化ビニル管・継手協会が運営するリサイクル事業にも早くから協力会社として参加しています。地域の資源循環を担って挑戦し続ける同社のこれまでの歩みと事業の現状を取材しました。
業績好転までの紆余曲折
「ここ2、3年で漸く仕事が安定してきました。モノが集まるようになったのと同時に、粉砕品の売り先に困ることもなくなりました。売上も伸びています。ここまで来るのに優に10年は掛かりましたね」
菊地社長は事業の現状についてこう説明します。冒頭で述べたとおり、ムサシノ化学は北海道の塩ビ管リサイクルを支える道内最大の拠点。とはいえ、そこまでに至る道のりは決して平坦なものではありませんでした。
同社の創業は1979年。最初は金、銀、アルミ、丹入(亜鉛の合金)など非鉄金属のリサイクルをメインに事業を展開していましたが、業績の低迷から樹脂サッシのリサイクルに着目。新たに設備を導入して、道内のサッシメーカーから出る工場端材のリサイクルへと方向転換を図ります。
「粉砕品を道外の再生塩ビ管メーカーに販売していたのですが、この仕事がキッカケになって塩ビ管リサイクルも手掛けるようになりました。塩化ビニル管・継手協会の協力会社になったのもこの頃のこと(1998年)。ただ、初めてはみたものの肝心のモノが全然集まらない。土地に余裕がある北海道では殆どが埋立処分で、塩ビ管のリサイクルなど誰も考えていなかったのです」

リーマンショックが転機に
転機となったのは2008年のリーマンショック。この国際的な金融危機によってサッシ廃材の入荷が激減し、機械が動かないという状況にまで追い詰められたことから、同社は改めて塩ビ管リサイクルに本腰を入れはじめます。
「依然として取引先は見付からず、建築業者や管工事業者、ゼネコンも相手にしてくれない。そこで、当時増えつつあった産廃の焼却施設に塩ビ管の分別をお願いすることにしました。塩化水素ガス等の問題などで塩ビの処理に困っていた施設があったからです。一方、時代とともに北海道でも埋立が難しくなってきて、埋立より原料化という動きが広がったことで、最終処分場や中間処理業者からもモノが集まるようになった」
紆余曲折の末に、ムサシノ化学の塩ビ管リサイクル事業はようやく軌道に乗り始めました。

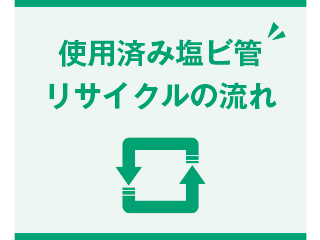

集荷した回収品をチェック

基準にもとづいてグレードごとに選別

破砕機に投入できるサイズに切断

洗浄して汚れや不純物を取り除く

粗破砕した後、さらに細かく粉砕

20mmのスクリーンを通して粒度調整

フレコンバックに梱包して出荷
リサイクル率97%
同社のリサイクルの流れは図に示したとおり。回収については、一部持ち込みもあるものの、「大半はこちらからトラックで回収に出向く」とのことです。
「排出先に選別、洗浄等の前処理は求めません。集めておいてもらったものは排出状態に関係なくすべて回収して、こちらで選別、前処理を行います。グレードはいろいろですが、10年掛けてノウハウを培ってきたので、どんな管でも大抵はリサイクルできる自信がある。VU600のような口径の大きなものでもOKです。うちでは回収品の97%を再資源化しています」
回収対象は北海道全域。広大な地域だけに、無駄な回収コストを掛けないような工夫も見られます。
「うちでは通常の産廃の収集運搬もやっているので、処分場に産廃を運んだ帰りに回収先を回るといった、ワンウェイでない、往復で仕事になるような方法を取っている」
望まれる行政の協力
最後に、塩ビ管のリサイクルを進めていく上で望まれることは何かを伺いました。菊地社長は「第一に欠かせないのは地域の行政の協力だ」として、次のように指摘しています。
「道内に関して言えば、現状では行政の協力は殆どない。例えば、道内のある市に古い市営住宅がある。その改築・建替えに伴って当然出てくるはずの使用済み管をうちでリサイクルさせてほしいと思って市役所に相談に行っても、まるで相手にしてくれない。本気で資源を大切にしたいと考えているのなら、行政は率先して循環の仕組みを作ってもらいたい」
このほかに菊地社長は、リサイクル品を生産するにあたり代価に対するグレードの要求が高すぎる日本の風潮もリサイクルを滞らせる問題のひとつに上げています。
「キレイ事でなく、資源を大切にして環境の改善に貢献したいという気持ちが強い。そういう思いがなかったらこの仕事はできない。社会に貢献しているという満足感がなかったら、この仕事はやっていけない」
非鉄金属のリサイクル時代も含めれば40年にわたって北海道の資源循環に貢献してきたムサシノ化学。菊地社長の言葉には、現場に根ざした人間の重みが感じられます。